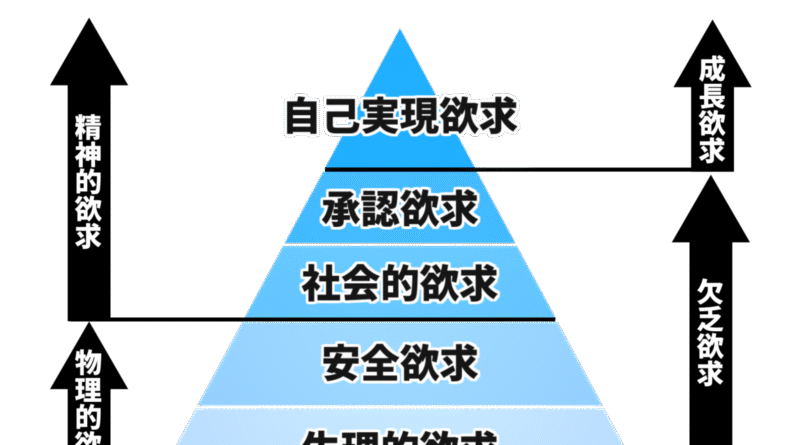自己人格確立論 客観視のその先へ
― 内在する自己を多角的に客観視することにより、その中心を自己と見出す ―
現代社会は、他者の視線に満ちている。
SNSに象徴されるように、私たちは常に「見られる自己」と「演じる自己」の間で揺れ動く。
その結果、内的な自分の声はかき消され、「自分とは何か」という問いすら曖昧になってしまった。
ここで私が提唱する「自己人格確立論」は、こうした自己喪失の時代に対する一つの応答である。
それは、「内在する自己を多角的に客観視することにより、その中心を自己と見出す」理論である。
人間の内面は、一枚岩ではない。
怒り、恐れ、創造、羞恥、欲望――それらはすべて、異なる人格的断片として自己の中に共存している。
多くの人は、この内的多面性を「不安定さ」や「矛盾」とみなす。
しかし本論では、それをむしろ人格の多層的可能性として肯定する。
なぜなら、自己の多様な側面を否定することは、自己の深さを否定することにほかならないからである。
哲学的に言えば、これは「存在の同一性」を固定的に捉える思考からの脱却である。
デカルト的自我は「思考する主体」としての一貫性を求めたが、
現代の私たちは、むしろ多様性の中での一貫性――すなわち動的な平衡――を模索すべき段階にある。
では、どうすれば多様な自己を統合できるのか。
その鍵が「多角的客観視」である。
これは、自己を観察する“観察者”としての立場を意識的に持ち、
感情や思考の揺らぎを一歩引いた視点から見つめる営みである。
ユングは「自己(Self)」を、意識と無意識を包摂する全体性と定義した。
しかし本論でいう多角的客観視は、その全体性を主観の中で自覚的に再構築する行為に近い。
すなわち、自己を“多面体”として観察することによって、
その内在的構造を理解し、中心へと向かう視座を得るのである。
具体的には、内省的な記録、瞑想的観察、他者との対話を通じ、
自分の感情・判断・欲望を一つずつ照らしていく。
そのプロセス自体が、「自己人格の形成過程」なのである。
多角的客観視を深めると、やがて一つの発見に至る。
それは、あらゆる思考・感情・欲望を観察している“何者か”――
すなわち、観察者としての自己の存在である。
この中心は、固定された本質ではない。
むしろ、流動する自己の諸側面を統合し続ける動的な均衡点である。
感情が激しく揺れ動く時も、観察者としての自分は静かにそれを見つめている。
ここにこそ、人格の核となる「確立された自己」の姿がある。
この自己は、仏教の「無我」に近い構造を持ちながらも、
完全な空ではなく、意識的統合の中心として存在する点で異なる。
すなわち、無我と自我の中間にある「覚醒的自我」としての位置を占める。
確立された自己は、社会的文脈から孤立しては成立しない。
むしろ、社会という外的環境との関係の中でその中心は試され、磨かれる。
職場や家庭、共同体における役割を果たすとき、
人は往々にして“演じる自己”に偏り、内的中心を見失う。
しかし、自己人格確立論の立場から見れば、
「役割の演技」と「中心の自覚」は矛盾しない。
むしろ、内的中心を保持したまま外的役割を果たすことこそ、成熟した人格のあり方である。
それは、社会に同調することではなく、社会と対話することによって自らを拡張する行為なのだ。
自己を確立するとは、自己に閉じこもることではない。
むしろ、内的中心を確立した者は、自己を超えて他者へと開かれる。
多角的客観視を極めた先に現れるのは、
「自己を通して世界を観る透明な意識」であり、
そこでは他者理解もまた自己理解の延長として成立する。
したがって、自己人格確立論の最終目的は、
「自己の確立」にとどまらず、「自己を超えた調和」――
すなわち、世界との動的平衡の中で生きる智慧を見出すことにある。
本論が示すのは、固定的な自己像ではなく、意識の中心を見出す方法論である。
自己は多面的であり、その多面性を客観的に観察することによってこそ、
変化の中に不変を見出すことができる。